
介護に向けた具体的な準備と対応策
1. 介護保険の申請(市区町村の窓口で申請)

介護保険の申請を考えるタイミング
介護保険の申請は、親が日常生活を送るうえで困難を感じ始めたときに考えるべきです。例えば、
- 食事や排泄、入浴が自力でできなくなった
- 認知機能が低下し、徘徊や物忘れが激しくなった
- 転倒が増えて骨折のリスクが高まった
- 一人での生活が難しくなり、家族の介助が必要になった
これらの状態が見られたら、早めに市区町村の窓口に行き、介護保険の申請を行うことが重要です。
2. 要介護認定の取得(ケアマネージャーと連携)
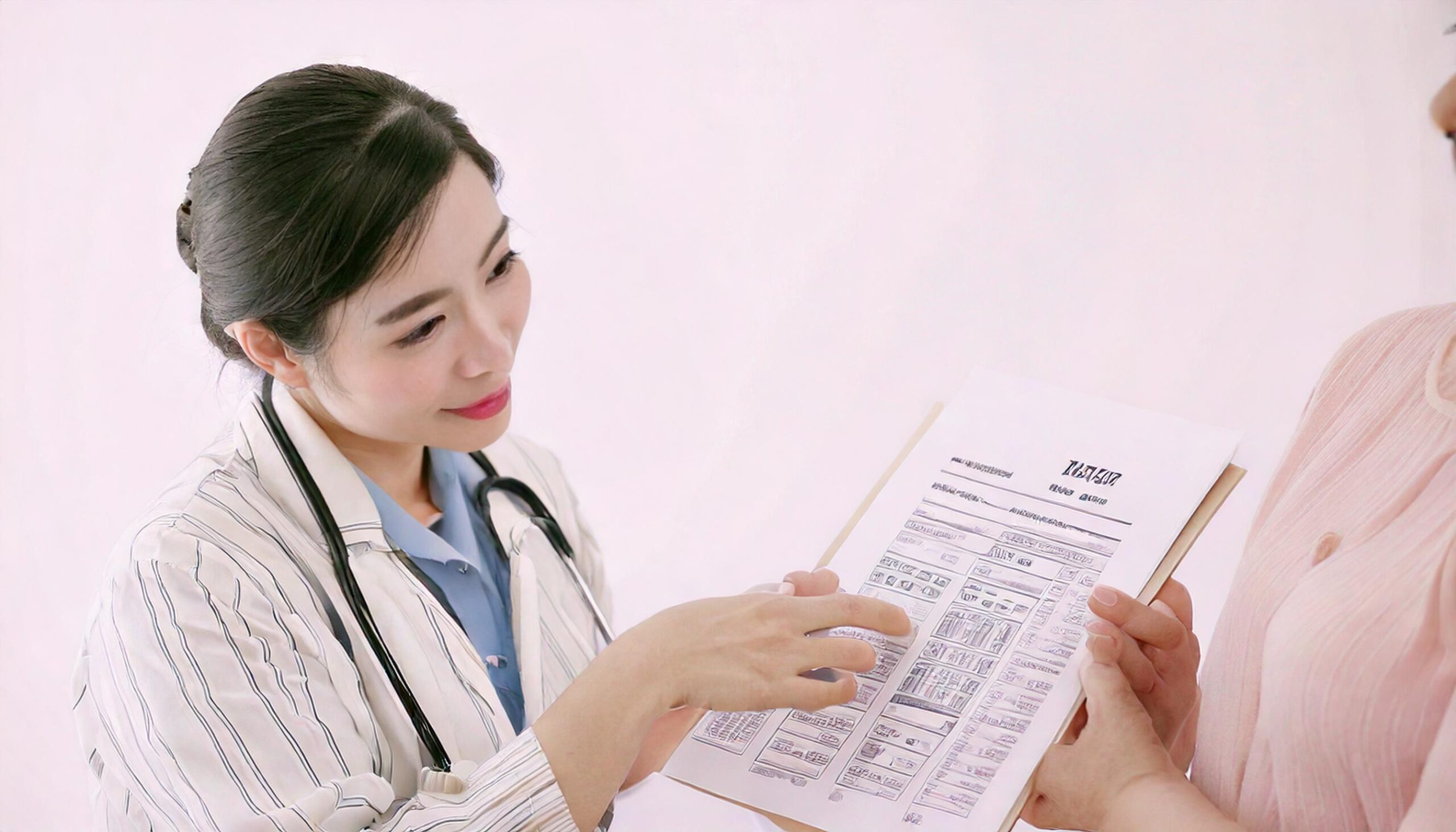
ケアマネジャーとの連携方法
介護保険の申請を行うと、要介護認定の調査が実施されます。その後、介護サービスを利用するためには、ケアマネージャーとの連携が不可欠です。
- 市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに相談。
- 市区町村の介護保険課:主に介護保険の申請手続きや制度の説明を行う。初めて申請を考えている場合や、制度の基本的な仕組みについて知りたいときに適している。
- 地域包括支援センター:より具体的な介護の相談窓口。介護サービスの紹介やケアプランの作成、要介護認定の手続きなど、実務的な支援を受けられる。
- 確定したら、ケアマネージャーを選定。(地域包括支援センターから紹介を受けるか、「介護サービス情報公表システム」を利用)
- ケアマネージャーと面談し、介護計画(ケアプラン)を作成。
- ケアプランに含める内容:
- 介護を受ける人の身体状況と生活状況の把握
- どのような介護サービスを利用するか(訪問介護、デイサービス、ショートステイなど)
- 介護目標(例:自立度の向上、家族の負担軽減など)
- 介護サービスの頻度とスケジュール
- 費用負担の確認
- 事前に考えておくこと:
- 親がどのような介護を希望しているか
- 家族がどの程度介護に関われるか
- 経済的な負担の確認
- 医療機関との連携の必要性
- ケアプランに含める内容:
- 介護サービスの手配を進める。
3. 介護サービスの選択(在宅介護・施設介護の決定)

施設介護になるまでのしのぎ方
施設に入居するまでの期間は、以下の方法でしのぐことができます。
- 訪問介護:ヘルパーが自宅に来て介助を行う。身体介護中心のサービスは30分あたり300~600円、生活援助中心のサービスはもう少し低い金額。
- デイサービス:日中のみ施設で介護を受ける。1回あたりの自己負担は600~1000円程度(介護保険適用後)。食費やおやつ代が別途発生。
- ショートステイ:短期間の施設入所で家族の負担を軽減。要介護1の場合、1日あたりの基本サービス費用は約600~1000円。これに加えて、食費や居住費が必要となり、総額は数千円程度になる。
介護サービスの月あたりの概算費用
一般的な利用回数をもとに試算すると、
- 訪問介護(月15回利用):約3,375円
- デイサービス(月12回利用):約9,600円
- ショートステイ(月7日利用):約5,600円
- 合計(訪問介護+デイサービス+ショートステイ):約18,575円
※介護保険適用後の自己負担額を想定。食費・居住費等は別途必要。 ※利用頻度は厚生労働省の統計データを参考。 参考:厚生労働省介護給付費等実態統計(https://www.mhlw.go.jp/search.html?q=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%B5%A6%E4%BB%98%E8%B2%BB%E7%AD%89%E5%AE%9F%E6%85%8B%E7%B5%B1%E8%A8%88&cx=005876357619168369638%3Aydrbkuj3fss&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=)
介護サービスの段階的な位置関係
訪問介護 → デイサービス → ショートステイ → 介護施設入居 という流れが一般的です。
- 訪問介護は、家族の支援がメインでありながら、一部の介護を外部に依頼する形。
- デイサービスは、日中のみ介護を受けられる形。
- ショートステイは、短期間の入所で、より本格的な介護が必要な場合に活用。
- 介護施設入居は、長期的な介護が必要になり、家族のサポートが難しくなったときに選択される。
このように、関わりの度合いや費用の観点から見ても、介護施設入居が最も家族の負担が少なく、費用が高くなる傾向にあります。
4. 親との会話(生活環境、医療方針)

親と子の希望のギャップと解決策
- 親:「家で暮らしたい」 → 現状維持を望むことが多い。
- 子:「施設に入居してほしい」 → 介護負担の軽減や安全面を考慮。
段階的に訪問介護、デイサービス、ショートステイを試しながら、現実を見据えた介護の形を模索するのが現実的な解決策です。
折り合わない場合の選択肢
- 次のきっかけまで何もしない:親が納得しない限り現状維持。ただし、転倒や病気などの大きな変化が生じた際に再度話し合う。体が弱ってきた実感を感じたりの不安が募ってきたことで、妥協が発生するのを待つ。
- 最低限のサポートに留める:訪問介護やデイサービスのみ利用し、親の意思を尊重しつつ、無理のない範囲でサポート。
- 絶縁(事実上の放置):親の意向に強く反発し、介護から手を引く。ただし、倫理的・法的責任が伴うため慎重に判断。同居している場合は基本この選択はとれない。別居していてもできるだけ避けたい。※毒親を除く※
- 成年後見制度の利用:親が判断能力を失っている場合、家庭裁判所を通じて法的に介護や財産管理を委託。
- 判断能力を失っているとされるための事実:認知症などの症状により財産管理や生活判断ができない状態が継続していること。
- 証明として必要なもの:医師の診断書、認知症の検査結果(長谷川式認知症スケールなど)、家庭裁判所への申立て書類。
- 成年後見制度を利用する手順:
- 医療機関で診察を受ける – 認知症の疑いがある場合、かかりつけ医や専門の精神科・神経内科で診察を受ける。
- 認知症の診断を受ける – 医師の診断書を取得し、認知機能低下の証拠を確保。
- 家庭裁判所へ成年後見の申立て – 必要書類を準備し、親が住む地域の家庭裁判所へ申し立てる。
- 審査と後見人の選定 – 裁判所の判断により、後見人が選定される。
- 親が検査を拒否した場合の対応:
- 穏やかに説得し、健康診断の一環として受診させる。
- 地域包括支援センターの職員や医師に相談し、第三者の説得を利用する。
- 法的な方法を検討(虐待リスクがある場合、福祉関係機関への相談も視野に入れる)。
このように、親の意向と子の負担のバランスを考慮しながら、現実的な対応を取ることが重要です。
5. 財産管理・成年後見制度の検討

財産管理をスムーズに進める方法
- 任意後見契約:判断能力があるうちに後見人を決める。
- 手続き:公証役場で公正証書を作成し、契約を締結する。判断能力が低下した際に後見人が活動を開始。
- 家族信託:信頼できる親族に財産管理を委託する。
- 手続き:司法書士や弁護士に相談し、信託契約を作成。信託銀行を利用する場合もある。
- 銀行の信託サービス:金融機関を利用して資産を管理。
- 手続き:金融機関に相談し、信託口座の開設手続きを行う。
介護費用を親の資産から負担する方法
介護にかかる費用を親の資産から負担する場合、適切な財産管理が重要です。
- 親の口座を活用する:
- 親名義の銀行口座から直接、介護施設やサービス事業者に支払いを行う。
- 事前に支払いがスムーズに行えるよう、金融機関に手続きを確認する。
- 親から通帳を預かる場合:
- 親の同意のもとで通帳を管理し、必要な支払いを行う。
- 注意点:判断能力が低下していると、後からトラブルになる可能性があるため、書面で同意をもらうことが望ましい。
- 親が「自由に使ってよい」と約束している場合:
- 口頭の約束だけでは法的な証拠にはならないため、委任契約書を作成するか、公正証書を作成しておくと安心。
- 成年後見制度が必要になる前に、親が元気なうちに話し合いを進める。
- 定期的な財産管理の見直し:
- 介護費用が不足しないよう、預金残高や収支を定期的に確認。
- 必要に応じて資産の整理や活用を検討(例:不動産売却など)。
- 成年後見制度の活用:
- 親の判断能力が低下した場合、家庭裁判所を通じて成年後見人を選定。
- 後見人が親の財産管理を行い、適切に介護費用を支払う。
委任契約書と公正証書の違い
- 委任契約書:
- 親が子に対して財産管理などの権限を委任する契約。
- 形式の自由度が高く、親が元気なうちに作成しておけば、家庭裁判所の関与なく柔軟に管理が可能。
- ただし、口頭契約だと後でトラブルになるため、文書化が必須。
- 作成費用:弁護士・司法書士に依頼すると5万~10万円程度。
- 公正証書:
- 公証役場で公証人が作成する公式な証書。
- 証明力が高く、将来的に紛争を避けるための証拠になる。
- 任意後見契約や金銭貸借契約、財産管理契約なども公正証書で作成できる。
- 作成費用:5,000円~3万円程度(契約内容や財産額による)。
6. 介護に関連する手続きのまとめ

| ステップNo | 内容 | 申請のきっかけ | 手続き先 | 手続き書類の名称 |
| 1 | 介護保険申請 | 日常生活での困難を感じ始めたとき | 市区町村の介護保険課 | 介護保険申請書 |
| 2 | 要介護認定の取得 | 介護保険申請後に要介護度を決める必要があるとき | 市区町村の介護保険課・地域包括支援センター | 要介護認定申請書・医師の意見書 |
| 3 | ケアプラン作成 | 要介護認定を受けた後、具体的な介護計画が必要になったとき | ケアマネージャー・地域包括支援センター | ケアプラン作成依頼書 |
| 4 | 介護サービスの選択 | 在宅介護か施設介護かを決定する必要があるとき | ケアマネージャー・施設・介護サービス提供事業者 | 介護サービス利用申請書・契約書 |
| 5 | 財産管理・成年後見制度の検討 | 親の財産管理が必要になったとき、または認知症の兆候が見られるとき | 家庭裁判所・弁護士・司法書士 | 成年後見申立書・医師の診断書 |
| 6 | 公正証書または委任契約書の作成 | 親の財産管理を明確にし、トラブルを避けるため | 公証役場・弁護士・司法書士 | 委任契約書または公正証書 |
7. さいごに

介護は突然始まることが多く、事前の準備が大切と言われています。とはいえ、一般的に介護が必要になってくる年齢かどうかや背中の丸まり、やり取りの鈍さ、運転の危うさ、など準備するきっかけはちらほら目についてきているとは思います。
各種制度を上手く活用しながら、家族全員で負担を分け、仕事との両立を工夫しながら介護に携わっていく必要があるでしょう。
これを書いている時点では、まだ実際に介護を行っていないので、実際に行うようになったとき、内容を修正したり別途記事を増やしていければと考えています。
それでは、また。
参考資料 厚生労働省:介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195509.pdf
参考資料 厚生労働省:地域区分について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000566688.pdf?utm_source=chatgpt.com
厚生労働省資料は、介護報酬や自己負担額の詳細をまとめたものです。見方のポイントは以下の通りです。
- 介護報酬単位(単位数)を確認
- 介護保険では、サービスごとに「単位数」が設定されており、地域ごとに異なる「単位単価」が適用されます。
- 単位数 × 地域単価 = 介護報酬(総額)
- そのうち自己負担分(1割~3割)が利用者負担となる。
- 各サービスごとの単位数を探す
- 訪問介護 → 資料の「訪問介護」部分を確認(ページ内で探す)
- デイサービス → 「通所介護(デイサービス)」の単位数を参照
- ショートステイ → 「短期入所生活介護(ショートステイ)」の単位数を参照
- 自己負担額の計算方法
- 自分の地域の「単位単価」を確認し、各サービスの単位数を掛け算。
- その金額の1割~3割が自己負担額。


