特性を見つめなおしたときに

話すなら深く、そして一人でじっくり考えたい。私はそういう人間です。仕事中はあまり雑談をしようと思わないのですが、雑談が苦手というより、仕事中は意味のある会話をしたいと思うのです。
気になったことがあれば即座に動きたいため、誰かと相談してから動くというプロセスはまどろっこしく感じます。一つ一つ相談しているといいタイミングで動けないと感じるため、できるだけ裁量があることを望みます。
また、絵や構造、仕組みで物事を考える癖があり、抽象度の高い議論は楽しさを感じるのですが、その反面、空気を読みながら感情を交えたトークで場を整える、という「いわゆるコミュニケーション術」には少し苦手意識があります。
とはいえ、飲み会など話すときは話すので、気分が乗った時やプライベートは特に無口というわけでもないです。
印象を鑑みるに、自分は「ソロ志向」なのだと思われます。
ソロ志向とはどういった特性か

一般的に言われるソロ志向の特徴は以下のようなものです。
- 一人で集中しているときに最も力を発揮できる
- 他人との調整よりも、個人で深く掘ることを好む
- 雑談より目的のある会話を好む
- 意見があっても、人に合わせて変えるより内省を選ぶ
一見すると「協調性がない」と捉えられがちですが、実際は他者との協力を望んでいないのではなく、「余計なノイズを排して本質的に向き合いたい」「仕事のクオリティを上げたい」だけなのです。
ずっと手をつないで歩く必要はなくて、目的地に合流できればそれでよいと思います。
とはいえ、深く掘る分だけ連携がしにくくなることがあり、雰囲気として「個人プレー」に見られてしまうというデメリットがあります。結果として、チームへの貢献が目立たず、他社貢献評価が比較的低くなりがちです。
チーム貢献は行っているはずだが伝わりにくい

案外ソロプレイヤータイプの人は、下記のようなことをやっていることが多い気がします。あくまで体感なので、私が見てきた範囲には限られるのですが、チーム内で割と手を動かす立ち位置にいると思っています。
- 会議の進行が曖昧なときに議題を整理し直し、資料を共有した
- 議論が噛み合っていない場で、両者の論点を接続する提案をした
- 他人の提案が通るよう、事前にロジックを一緒に整理した
- トラブルを未然に防ぐため、チェックフローを裏で整備した
特に最後のような「火消しではなく予防」に関する対応は、なにも起きなかったがゆえに簡単な仕事に見えるのが残念なところです。
実際は、先回りして仕組みを整えたからこそ混乱が起きていないのですが、それが伝わらない限り「評価されない仕事」として埋もれてしまいます。
おそらく、特性としてコントロールされることをあまり良しとしない傾向があるため、自発的に先回りするのだと思います。すると、先回りしたことで、見たときには何もないという状況が出来上がります。
ソロ志向でもリーダーシップが必要な理由

チーム貢献、という形ではインパクトが弱い動きになると思います。そのため、リーダーシップをとっていく、というくらいの動き方でチーム貢献しているような印象になってくると思います。
しかし、そこまでしてリーダーシップを発揮する必要があるのかと問われると、やりたいことがあるなら必要と答えるでしょう。
というのも、自分が描いた「仮説」や「正しいと思う設計」を具現化するためには、他者との協働と牽引が必要な場面にも出くわすからです。どれだけアイデアがあっても実行できる状況にならないと実現できません。
また、一人で完結しようとすればスケールの小さな成果にしかなりません。とはいえ、それは一人で作れないというよりタイムリミットに間に合わないから、ということだと思ってはいます。
また、現在の働き方で特にリモート環境では、「普段の振る舞い」が見えません。
- 日々のちょっとした気遣い
- 雑談の中でのフォロー
- 空気を読んだ進行の補助
こういった要素が、見えにくくなっているのです。見えるタイミングはオンラインMTGだけになってしまうため、そこでの映り方次第では大きく評価を下げることにもなりかねません。
ということは、チーム貢献はほかの人から言伝してもらわないと伝わることはないのです。商品が売れるためには、レビューを書いてもらわないといけないようなものです。
だからこそ、ソロ志向の人こそ「意図して影響力を持つ」ことが重要になります。
そして現実問題として、給与水準や待遇を上げていくには、マネジメント能力や影響力のある立ち位置が必要です。専門職でもない限り、評価されるための戦略が必要になります。
「伝え方」が要になる
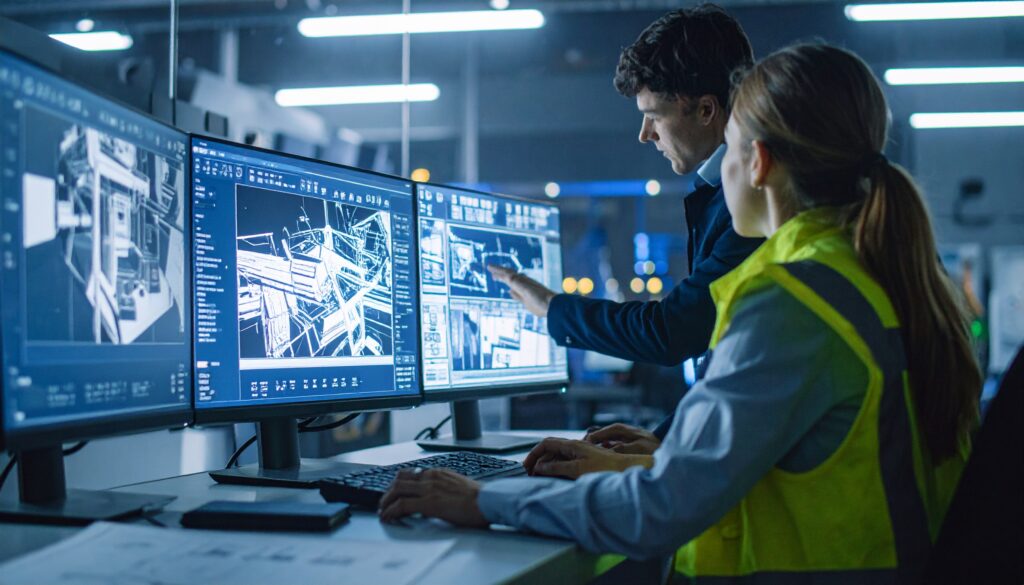
普段の行いが見えにくいということは、数値はデータで見せることができるものの、言語化しにくい要素は捉えにくく、どうしても会話で判断するしかありません。
会話のタイミングもなかなか限られているかと思うので、「伝え方」に磨きをかけるしかありません。どちらかというと、減点されることを避けるミッションです。言い方は大事だと巷でもよく言われますね。
例えば:
- ×「この案は無理です」 → ◎「方向性いいですね。さらにリスクを補完する視点としてこちらも検討してみませんか?」
- ×「中途半端ですね」 → ◎「すごいですね。もう一歩踏み込むとさらに見える景色が変わりそうですね」
思ってもいないことを言う必要はありません。型としては、まず肯定。その後に求めるクオリティの提案をするような形です。ついつい、課題を解決していこうとすると正直に答えすぎてしまう可能性があるので、フィードバックも型を覚えます。
正直なところ気分が乗らないときは難しかったり、TPOによって声が小さくなってしまうこともあるかと思います。
ですので、よい伝え方ができるように、自分でも印象が良いだろうな、と思う話し方ができそうなタイミングに合わせて話せるとよいでしょう。タイミングが悪ければ、「また確認します。」などでいったん機を見ましょう。
実はできていない報告

自分では「ちゃんとやっている」「貢献している」と思っていても、それが評価者やチームに伝わっていない。その原因の多くは、「言語化して伝えていない」ことにあります。
特に、ソロ志向の人や誠実さを重視するタイプは、「成果で語る」ことを美徳としがちです。しかし、現実の評価は「見えること」「届いていること」に基づいて下されます。「目に見える情報」「耳に入る言葉」こそが評価の基準になりやすいものです。 無意識のうちに、こんな習慣が染みついていないでしょうか。
- 自分の貢献は、見ればわかるはずと思ってしまう
- 日々の整備や調整は当然のこととしてスルーしてしまう
- アピールすることに気恥ずかしさを感じてしまう
- 「気づいてくれる人だけ気づいてくれればいい」と思っている
こうしたスタンスは誠実さの表れでもありますが、本来評価されるべきことが無かったことになりがちです。評価とは、「行動」×「伝達」=信頼で構成されていることを忘れてはいけません。
確かに、何も言わずともわかってくれる、粋な関係は望ましいですが、慌ただしい日々のなかで悪気なく見てないことも大いにあり得ると思います。
そこでギスギスしてしまうのではなく、しっかりと言語化して、自分の行動を見える化していく必要があります。
見える化はアピールではなく構造整備
重要なのは、行動したことを声高に叫ぶことではありません。おそらくうるさいです。淡々と確実に「伝わる構造」を組み込んでいくことです。たとえば次のような工夫です。
- 対応したことはさりげないトーンで必ず報告する。
- 提出物は「こういう意図で整理しました」と添える
- 会議の議事録に、自分が準備した項目や調整点を自然に記載する
- 他メンバーの提案がスムーズに通るよう、裏で支えた点を補足情報として共有する
これらはすべて、「貢献の事実を届ける仕組み」であり、ただの自己主張とは少し違います。
報告・共有・可視化は、自分の役割と貢献を、組織の中で流通可能な形に変換する行為です。「自分で動いて整えておいた」ことも、「誰かを支えるために仕組みを補強した」ことも、それが伝わって初めて「組織としての前進」になります。
そしてこれは職場だけの話ではありません。たとえば夫婦関係でも同じようなすれ違いがよく起こります。
家庭のどこかを掃除しておいたとしましょう。自分としては、「汚れてきたことに気が付いたから、ついでにやっておいた」というささやかな気遣いのつもりだったとします。しかし、相手は気づかない。そのまま通り過ぎてしまう。
モヤモヤが残ってしまう。
ここで必要なのは、ほんの一言。「ちょっと気になったから掃除しておいたよ。」
これだけで、相手が気づけていなかっただけなら、伝えることで関係がなめらかに循環するのです。悪気がないことがほとんどだとは思うので、まずはこのちょっとした対応で、関係性がスムーズになります。
そして、おおむね評価する立場の人は、多忙であり、情報も錯綜しています。その中で、「なんとなく伝わるだろう」は通じにくいのが実情です。むしろ、伝え方まで含めて日々の行動指針に組み込む必要があります。
ただ、工夫で何とかなるのは、行動の価値が理解できるときに限ります。行動の価値がわからない相手や、テイカー気質のやってもらって当たり前と思っている相手ではないときです。
「職業は俳優」としてリーダー像を演じてみる

しかしそうはいっても人は、すぐには変われません。仕事に集中しているとき、タイミングによってはすぐさま思考のチャンネルは切り替わらないと思います。 ですので、「少し演じてみる」くらいのスタンスも時には必要です。
- 髪型や服装を変えて、自分に「違うキャラ」を許す
- 発言スタイルや言葉遣いを変える
- 「こうあるべき上司像」をなぞってみる
最初は気恥ずかしくても、「俳優のつもり」でやってみる。報酬が満足できていれば演じる動機にもなるはずです。逆に今、納得できていない状況なら、「変化を起こして報われる形」を自分で設計する時期なのかもしれません。
理想のリーダー像は、過去の経験から形を変えていく

そして、目指すリーダー像は、過去の上司や同僚との関わりから生まれてくるものです。うまくいかなかった関係性、評価されなかった悔しさ。そうした経験が、「どうありたいか」を少しずつ輪郭づけてくれるのです。 私が望むリーダー像は下記のような形です。
- 構造を確実に理解し、対話を大切にする
- 妥協せず、相手を置き去りにしない
- 静かに、誠実に、責任を引き受け、引き受けさせる
- 現実的に課題対策の方針を明確に示す
- 今後の発展イメージを共有し、希望を構築する
ソロ志向の人にとって、言わなくても伝わる関係性は理想です。しかし、組織という場では「伝える設計」を怠れば、誤解や過小評価につながりかねません。
伝えることは媚びではなく、足場や道筋を整えること。行動可視化は信頼の土台づくりです。それを意識して仕事の設計に組み込んでいくだけで、評価や周囲の見え方は大きく変わっていくのではないでしょうか。
ソロ志向でありながらも、チームと共に「理想を現実に変えていく力」。一つ一つリーダーシップにつながる土台を積み上げていきましょう。


