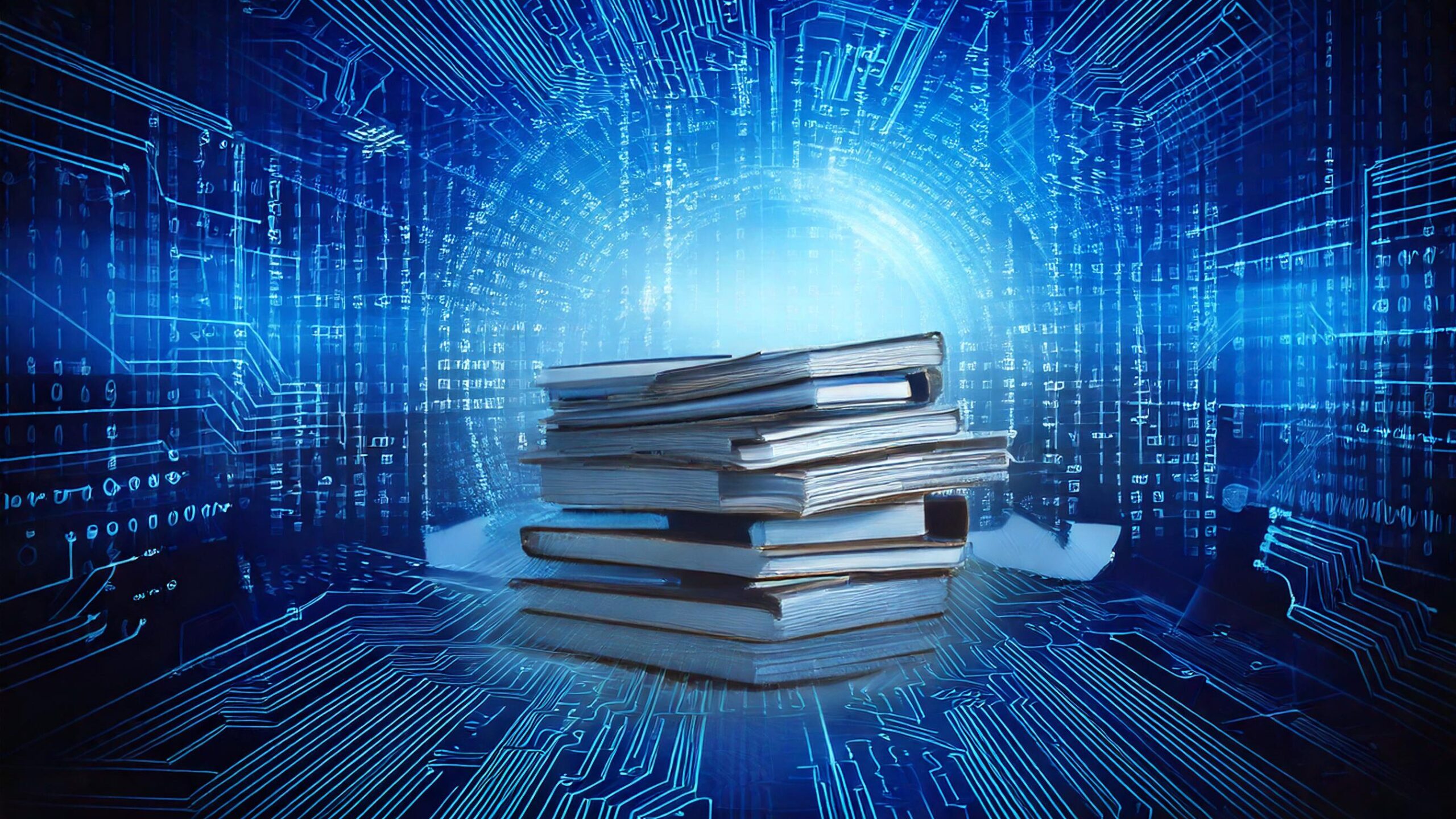
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、紙ベースの帳簿や証憑を電子データで保存する際の法律や規則を指します。日本では、電子帳簿保存法に基づき、適切な保存や運用が求められます。この方法を適用することで、経理業務の効率化や保存コストの削減が期待できますが、一定のルールや条件を守る必要があります。管理の目的と要点は下記です。
- 正確性の担保:元データと改ざんされていないことを示すためのタイムスタンプ付与や電子署名。
- 検索性の確保:必要なデータを迅速に検索・確認できる仕組み。
- 保存期間の遵守:法律で定められた保存期間(通常7年間)の維持。
- 適切な保存形式:データ汎用性(PDF、XMLなど)。
電子帳簿保存法について、詳しくは国税庁サイトをご確認ください。

具体的に必要な作業は何か
先述した要点を守る必要がありますが、具体的な作業としては何をしたらいいのでしょうか。副業やフリーランスの際に導入するステップは以下の通りです。
- PDFファイルでローカルに保管する
- フォルダ構成、ファイル名をルールに沿って管理する
- PDFファイルにタイムスタンプを付与する
- 管理するファイルは7年間保存する
こう書いてみるとシンプルですね。実務上に個人的に影響があったポイントとしては一つ目の「正確性の担保」の要件を満たすために、「タイムスタンプ」が必要になったことでしょうか。
フリーランスや副業でWeb関連の作業を行っていれば、また、ECサイトで仕事に関係する経費を使ったときは、おのずと請求書や領収書回りはPDFで保管しつつ適宜プリントアウトしたりしていたことでしょう。 さて、それぞれのステップについてどう手を動かしたらよいか詳細を見ていきましょう。
PDFファイルでローカルに保管する
サーバーや水道高熱費、Webサービス、ECサイト、にてアカウント管理ページなどから、請求情報が確認できるかと思います。おそらくダウンロードできるボタンがあったりするので、そこからPDFファイルをダウンロードできるでしょう。
もし、そういったボタンがなければ、プリントアウトする手順で出力をプリンタではなくPDFを指定すれば、開いているページをPDFファイルとしてダウンロードすることができます。

フォルダ構成、ファイル名をルールに沿って管理する
ダウンロードしたファイルをPCのローカルに保管します。もちろんクラウドサービスに保管するならそれはそれでOK。ただ、容量が許すならローカルにまず保管しておくことが、後々確認するにしても、バックアップの観点でもスムーズだと感じます。
そしてファイルの管理の際にルール上気を付けることは下記の3点です。
- ファイル名には日付、内容、相手先名などを含め、内容を一目で識別可能にする。
- フォルダ構造と組み合わせて、体系的な分類を行う。
- 改ざん防止策やアクセス履歴の管理が必要。
上2つはPCローカルだけで可能なのですが、最後の改ざん防止などのエビデンス対応に注意が必要です。ダウンロードした請求書の場合も、レシートをスキャンしてPCに取り込む場合も、PDFデータにはタイムスタンプという証明を付与する必要があります。
その証明を付与するオーソドックスな方法が、電子帳簿保存法に対応しているマネーフォワードクラウドboxなどのクラウドサービスにPDFデータをアップロードする方法です。
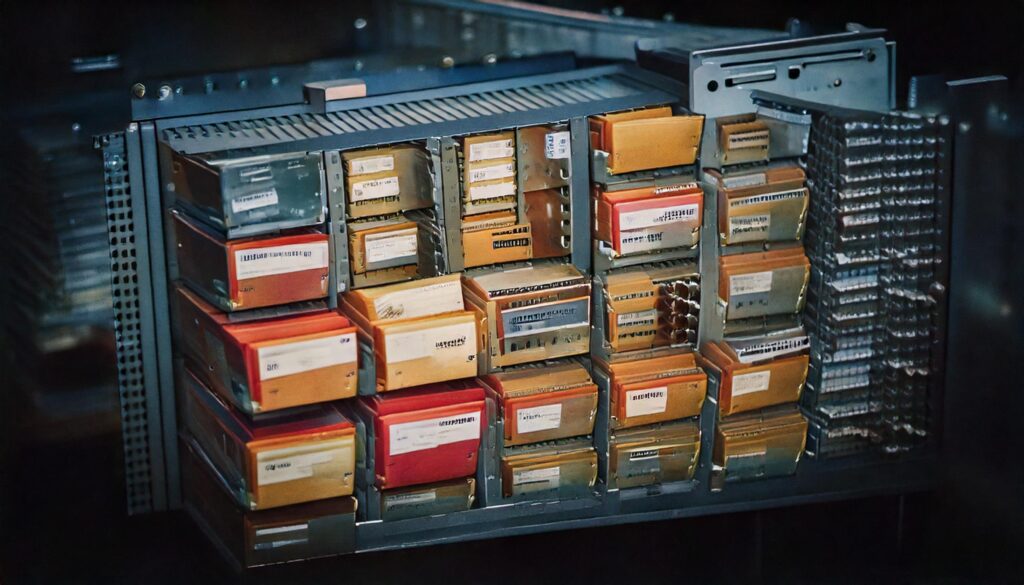
フォルダ構成、ファイル名の一例
さて、以下に実際にファイルを管理する構成の一例を記載しておきます。仕事でファイル管理をされている方は、ツリー状の管理方法に馴染みがあると思うので、ルールを押さえつつ把握しやすい管理にするとよいでしょう。
経費管理
├── 2025
│ ├── 01_請求書
│ │ ├── 2025-01-10_Amazon_請求書.pdf
│ │ ├── 2025-01-12_Google_請求書.pdf
│ ├── 01_Webサービス
│ │ ├── 2025-01-05_Adobe_請求書.pdf
ここで私は一つ疑問が生まれます。昨今のグローバル化。外国、特にアメリカのイノベーションが日本を蹂躙しているので、アメリカ企業のサービスを使うことが大いにあり得ると思います。
日本のBtoBの企業相手ならさほど困らないのですが、株式会社とするのか、Incなどとするのか迷うところです。というのも、サブスクリプションサービスなどの提供先は支店である日本法人が相手先となるのか、それとも、本社が相手先となるのかです。

外国の企業はどう記載すればよいか
外国企業との取引については、以下の点に注意する必要がありそうです。
- 取引先名の表記:契約書や請求書に記載された正式名称(LLC、Inc.などを含む)を使用。
- アルファベット表記が基本ですが、翻訳名を「併記」してもOK。
- 国や法律により異なる場合があるため、現地のルールを確認。
この注意点を簡単に押さえるとすると、請求書をダウンロードしたら、その請求書に記載されている支払い先の企業表記をそのまま流用すればよい、ということになります。
請求書の発行元が日本法人であれば「○○○○合同会社」を記載し、本国法人であれば「○○○○ Inc」を記載するのが適切です。
そのうえで、日本語表記をプラスアルファで記載してもOK、というのが基本ルールとなるようです。
そして、同じ企業は同じ表記で統一することが重要です。補足的に日本語表記を入れてしまったなら、その対応を続けなければなりません。帳簿仕訳のルールと原則は同じです。
さいごに
また、おいおい税務署などに確認するなどして、適宜齟齬や関連する情報を精査していければと思います。


