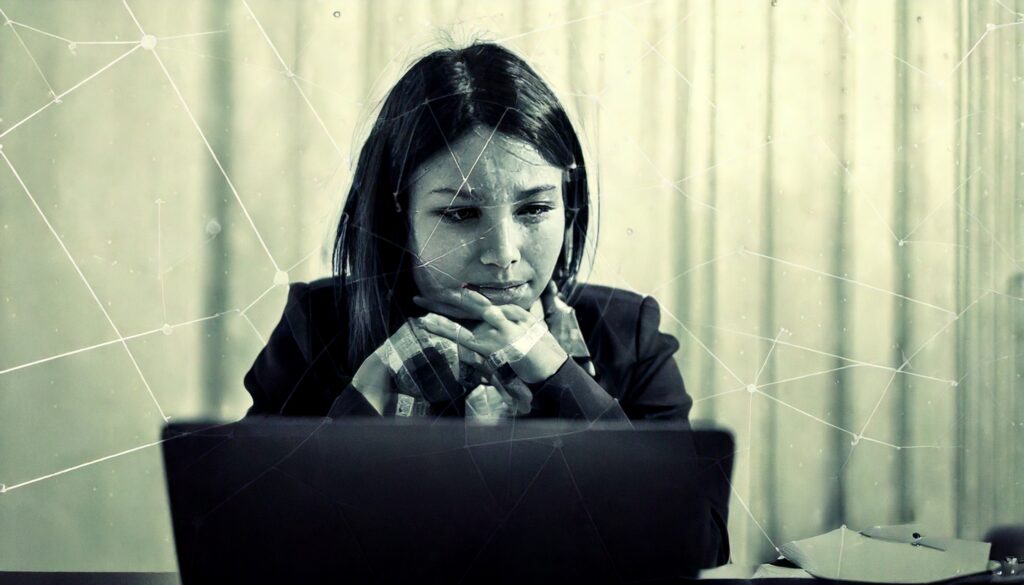
働き方に変化をもたらすために
働き方に変化をもたらしたい。
職場である程度の期間働いていると、少なからず不満や改善案が出てくるものです。完璧な職場はおそらく存在しないので、日々改善を心がけていく必要があるのですが、肩書や役職がないと核心を突いたアプローチはできません。
しかしながら、だからといって「何もしないでいい」という理由にはなりません。黙々と仕事の不満を甘んじて受け入れているだけでは、不満が解消されることはあまりないと思うからです。
仮に、自動的に不満が解消しているとしたら、同じ不満を持っている誰かが自分の知らないところでアクションを起こしているはずです。肩書がなくてもできることは少なからずあるはずです。
「自分の働き方を変える」というテーマに取り組もうとするとき、最初に意識したいのは「周囲に与える影響を変えること」です。自分だけが変わっても、周囲の環境が同じままだとすぐに元に戻ってしまったり何も変化が起こりません。
つまり、働き方の本質的な変化は、職場の文化やチームの空気感が変わることとセットで成り立つのです。そのためには、自分が周囲に影響を与える「存在」になっていく必要があります。
ここでいう影響力とは、誰かを強制的に従わせるような力ではなく、提案に耳を傾けてもらえる、改善案を形にしやすくなる、周囲の雰囲気を少しずつ前向きにできるような、日常の中でじわじわと効いてくる力です。
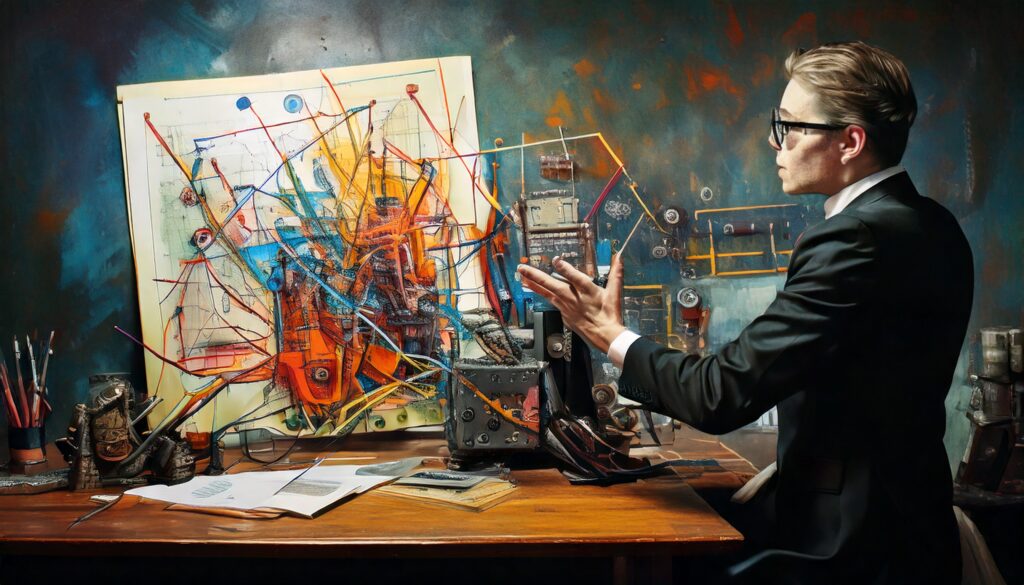
役職がなくても変化は起こせる
もちろん、会社や組織の構造によっては「その一言を言える立場」でなければ話が通らないこともあります。が、それは「すべての変化に肩書が必要」ではないということでもあります。
たとえば、日々の業務の進め方や、チーム内のちょっとしたルール、コミュニケーションの取り方などは、役職に関係なく改善の余地があり、それを提案することは誰にでもできます。
なお、提案先は、上長、リーダー、同僚、のうち影響力を持っている人です。周囲を見渡してみて、影響力がある人というのはしばらく働いてみると見えてくるところがあるかと思います。
自分の社歴などのポジションによって、ダイレクトに上長へ、ルールがあるからまずはリーダーへ、上長も意見を参考にする業務の影響力が強い同僚へ、スムーズに進みそうな順番で提案をしていきます。
もし、大きな会社で人事部が何かヒアリング形式のことをやっていたら、そちらにもエビデンス的に提案を投げておくとよいでしょう。もしくはシステム開発の際に社内アンケートがあるかもしれません。そちらにも投稿をしておくとよいでしょう。なお、おそらくこういったところだけに提案しても大衆のうちの一人で効果は薄いので、だれかへの提案と並行して行っておく必要があるでしょう。
実際、小さな改善提案やちょっとした工夫を重ねることで、チームの雰囲気が変わり、やがてその人の存在感も変わっていくということはよくあります。肩書のない人でも、積み上げによって信頼と発言力を得て、変化を起こせるのです。
暗黙の組織のルールが、同僚の仕事のやり方をインスパイアしあうことで作られていって、中間点のようなルールが浮かび上がってきて、それをもとに管理職が正式なルールを敷く、という流れもあるので、黙々と背中で語るという方法もあります。
これは、実際に仕事をまず自分が思うやり方で進められる環境にあるときには有効な対応で、実際施策を導入してもトライアンドエラーを重ねていくことで当初の形とは大きく変わったり、ひたすらシンプルになっていたりします。
ただし、大きな仕組みをひっくり返すような改革や、予算の決裁に関わるような話は、やはりそれ相応の「権限」が必要です。そこまでを求めるなら、ポジションを目指すことも必要になってはきます。
しかし、望むポジションはいつ手に入るかわからないものですし、働きやすくしたいだけで役職までは欲しくない。というようなケースもあることでしょう。できるだけ肩書に頼らない改善の方法を考えていければと思います。

仕事のクオリティを高めることが第一歩
では、どうすれば肩書に頼らずとも影響力を持つことができるのか?
答えはシンプルです。まず、自分の仕事のクオリティを高めること。仕事がきちんとできている、という信頼がなければ、どんな提案も響きません。
たとえば資料ひとつ作るにしても、「あの人が作ると安心」「使いやすい」と感じてもらえるようなレベルを目指します。自分が直接関わらない作業でも、何かしらアドバイスをしたりサポートできるようになると、「頼りにされる人」というポジションが築けます。
そうなると、自ずと発言が通りやすくなり、ちょっとした提案も「それならやってみようか」と受け入れられやすくなるのです。私自身、業務のクオリティがある程度担保されてきた段階から意見が通りだした実感があります。
ただし、営業畑の人が技術畑の人のことがよくわからない(理解しようとしない)など、自分の仕事の出来が全く分からない人しかいないなら、おそらくプレゼンやアピールを磨いたほうがよいでしょう。口下手状態だとかなり苦しくなります。

発言力を上げることにつながる
発言力とは、声の大きさでも饒舌さでもありません。「この人の言うことなら、検討に値する」と思われる信頼の蓄積こそが、発言力です。
では、その発言力はどうすれば高められるか?ポイントは「貢献度」と「面倒臭さ」のバランスです。
いくら仕事ができても、「口を出すだけで自分は動かない」「マウントをとるだけ」という印象を与えると、協力者が減っていきます。逆に、多少押しが弱くても「この人がいると助かる」と思われるように貢献度を高めることで、自然と話を聞いてもらえるようになります。一見、地味な積み重ねですが、それがまずはいちばんです。
しかしながら、時には多少強引に進めるような時も必要だったりします。というのも、やんわりと言うだけでは、決定権を持つ人や影響力がある人の数多あるタスクの中の、自分の提案が上位に上がっていかないときがあるからです。
これは、どちらかというと少数派になっている困りごとが不満として発生しているときに起こりえる事柄です。困りごとを解消しても喜ぶ人数が少ないため、上長などにとっての費用対効果が低く感じられているので、限られた行動リソースの範囲に自分の提案が入ってきません。
できることなら、「そのまま耐えてほしい。」そして、「いつの間にか課題が立ち消えになってほしい。」そういった状態になっているため、困りごとを解決したい場合は多少喚くようなアクションを取り入れることで、「まずは黙ってほしい。」という状態に変化してもらいます。
一時的に不快感を与えて解決の優先度を上げてもらうのです。とはいえ、これは普段の関係性や貢献度が足りていないと、ただ単にうるせえやつになるので注意が必要な点がありますが、こういったことをしないと、基本的に自分だけが困っているようなことはおそらく解決することはなく、耐えるだけになります。
もちろん、職場で自分が置かれた立場によっては、ただひたすらに耐えるだけの時期を過ごさないといけないときもあるとは思いますが、自分にとっての困りごとなので仕事中のストレスは大きいはずですので、できる限り耐えるだけの状況からは早めに脱却しないと、今いる職場で仕事を続けていくことが困難になるでしょう。

無理に好かれようとしないが、嫌われてもいいことはない
ちなみに、職場では、「全員から好かれる」必要はありません。しかし、「多くの人に嫌われる」ことは、避けられるなら避けた方がいいです。
これは、好かれても自発的に評価されることよりも、嫌われて悪評が入る可能性のほうが高いからです。ネガティブなリークは少数なら発信者がマイナスになることが多いかと思いますが、数が集まってしまうと本質の内容にかかわらず、影響力は妨げられますし、役割を任命する権限を持つ人も嫌われている人に影響力を与えることはできなくなってしまいます。
特に、何かを変えようとする場面では、誰かの利害を踏むことになります。そこで敵を作ってしまうと、変化の芽はつぶされやすくなります。私自身も、おそらくこれで過去失敗しています。
そのためにも、「一貫性がある」「感情的でない」「今かどうか」という点は意識したいところです。職場における影響力は、人間関係のバランスの上に成り立っているからです。

能力の高さをアピールしても鼻につく
よくある落とし穴として、「仕事ができることを前面に出す」という行動があります。自分の努力を知ってほしい気持ちは自然なものですが、あまりにも自己主張が強すぎると、周囲からは「鼻につく」と受け取られるリスクがあります。
むしろ、周囲が「この人、すごいな」と気づくくらいの控えめさの方が、組織では長く信頼されやすい可能性があります。自己評価よりも、他者評価が先に立つというのが、組織の中の暗黙のルールともいえます。
とはいえ、ここは承認欲求が満たされていない背景がある、仕事に対する責任感が強すぎる、という課題も隠れているので、また別途深堀りしてみたいと思います。
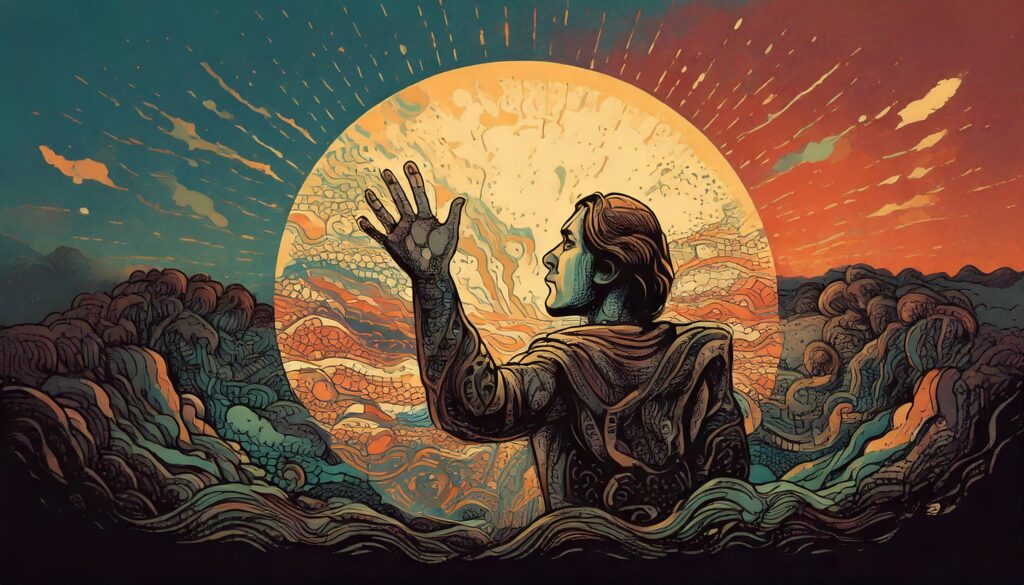
かなわないこと前提で意見を出すこと自体は必要
意見を出すときは、「かなわないかもしれない」と思っていても口に出すことが大切です。そうでないと、現状が変わることはないからです。
もちろん、提案がすぐに採用されることはないかもしれません。しかし、何度か出すうちに「また言ってるな」ではなく「それだけ言うには大事なことなのかもしれない」と受け止められるようになっていくケースもあります。
意見を出すことで、今後の動きに参加できるきっかけにもなります。変化のタネは、まず声に出すことからしか始まりません。
権限を持っている人とコミュニケーションをよくとる
職場で影響力を発揮するには、権限を持つ人と日常的にコミュニケーションをとることも不可欠です。
これは、おべっかを使うという意味ではありません。意思決定者がどんなことに関心を持ち、どんな価値観を持っているのかを把握することで、提案の伝え方やタイミングが変わってきます。
また、権限者との信頼関係があればこそ、「あの人が言うなら検討しよう」という空気が生まれます。
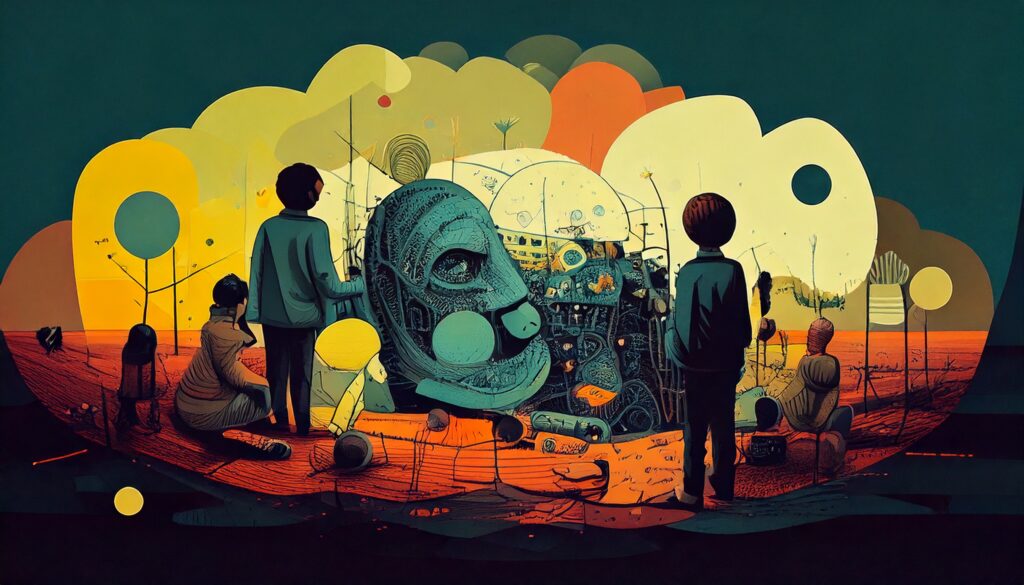
タバココミュニケーションが有利なのはこの点にある
近年では減少傾向にありますが、「タバコ部屋」や「喫煙所」での会話が重要な社内ネットワークになっていた理由はここにあります。
偶然を装いながら雑談し、ゆるやかに情報共有し、ちょっとした相談を気軽にできる空間がそこにあった。いわば非公式な根回しの場として機能していたのです。
喫煙者でなくても、休憩時間やすれ違いの中で、同じような雑談ができる余白を持つことで、権限を持つ人との距離感が変わることがあります。
直属の上司と敵対しないこと
そして最後に、どんなに理不尽でも直属の上司と敵対することは極力避けた方が賢明です。
直属の上司は評価に直接影響する存在であり、彼らとの関係が悪化すると、発言力どころか日常業務そのものが進めづらくなってしまいます。
違和感がある場合は、ストレートな対立よりも、「一緒によりよくするためには?」という建設的なスタンスで関わることがポイントです。
そうはいいつつも、会話する中や行動を見る中で「あ、無理だ、この人。」と思ったら、長期戦を覚悟して淡々と日々を過ごすか、そのコミュニティからの離脱を真剣に考えたほうが良いかもしれません。
そのくらいで接しているほうが、温度感が丁度よくなって適度な距離感を保ちやすくなると思います。

少しずつできること
肩書きがなくても、職場の働き方を変えていくことはできます。そのために必要なのは、地道な信頼の積み重ねと、定期的な発信。そして要所要所での周囲とのバランス感覚。
影響力で空気を動かしていく——それが、今の職場で試すことのできる変化の起こし方なのだと思います。


