なんとなく安全な人が選ばれるという感覚

役職に就いている人を見て、「あの人はまあ妥当だよね」と感じる場面は少なくありません。特段キラキラとした才能があるというわけではないが、波風を立てない。組織の空気感や社風とマッチしている。そういった意味での無難な人が、役職者として据えられていることが多いのではないでしょうか。
もちろん、明文化された評価制度が存在していたとしても、それだけで役職が決まるわけではありません。評価の裏側には、さまざまな「非言語的な納得感」が横たわっています。
評価されたい人が見ておくべき3つの視点
役職につくために、「こうすれば絶対に評価される」という明確なルートがあるわけではありません。ただし、多くの組織に共通する見えない評価軸のようなものは存在しています。
私がこれまでの職場経験や、さまざまなビジネス書から整理して見えてきたのは、以下の3点です。
- 序列を意識できているか(熱意との差し引きがプラス)
- 面倒ごとを起こさないか(魅力との差し引きがプラス)
- 仕事が目立っているか(水準との差し引きがプラス)
仕事ができるかどうかは実は優先度が低いんですね。組織という枠組みで評価される以上、まずは「その場において秩序を守れる人か」という点が土台になっているのです。
あくまで、1つめと2つめができていることが多いので、3で比較がされる状態になっているだけです。
1. 序列を意識できているか

比較的能力が高いと評価を受けている人は、時にこの点を軽視しがちです。正しさや効率性を追求するあまり、指示系統を飛び越えてしまったり、組織内での優先順位を無視してしまう可能性があり得ます。すると、「協調性がない」「空気が読めない」といったネガティブな評価につながってしまいます。
日本的な組織では特に、目立ったコンプライアンス違反がなくても、暗黙のルールに違和感を与えるだけで足を引っ張られることがあります。熱意が強ければ強いほど、慎重さが求められる局面です。
2. 面倒ごとを起こさないか

ここでいう「面倒ごと」とは、トラブルやクレームだけではありません。業務の属人化、無用な改革案、周囲との軋轢なども含まれます。優れたスキルを持っていても、業務をややこしくしているように見えてしまえば、評価は伸び悩むでしょう。
反対に、地味でも組織全体の安定運用に貢献している人は、確実に信頼されていきます。職人的なこだわりが悪いわけではないのですが、あまりに突き詰めると「チームを崩す人」という見方をされるリスクがあるのです。
3. 仕事が目立っているか

最終的には「この人、仕事できるよね」という実績がものを言います。ただし、ここで重要なのは“目立っているか”という点。どれほど高品質なアウトプットであっても、評価者の目に届かなければ、それは存在しないのと同じ扱いになります。
求められる水準を上回る仕事をしていても、共有の場で紹介されていなければ、評価されない。自分の仕事の価値を「見せていく」ことも、組織の中では重要なスキルの一つといえるでしょう。
見えているデータと見えていないデータ
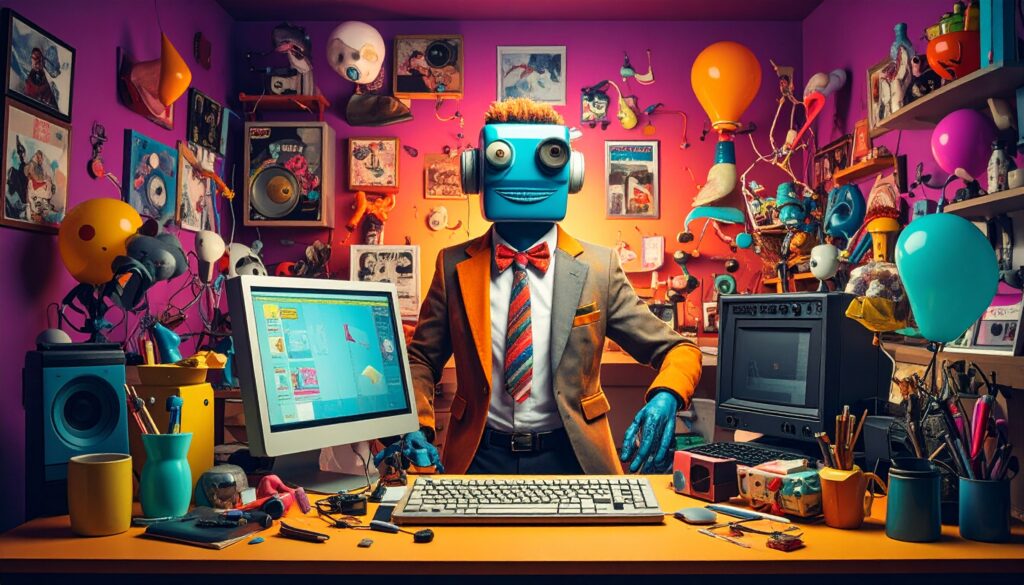
人事評価の話になると、つい「成果」や「実績」といった話に終始しがちですが、実際には1と2のような暗黙のデータが評価のベースになっています。これらは人事制度の中では明記されず、個々の評価者の判断に任されている部分が大きいのです。
そして、評価を行うのは評価関係者であって、職場の同僚がそのまま評価者になるわけではありません。
仮に同僚が「Aさんってすごいよね」と思っていたとしても、その声を評価者がどう受け取ったか、そこが評価への入り口になります。つまり、同僚の評価には間接的なフィルターしかかかりません。
また、利害関係が絡むと、そのフィルターにバイアスが生じます。さらに、評価者自身が実際に評価対象者を日常的に見ているかどうかによって、認識のズレが生じるのです。
「人間性」は関係あるのか?

「自分は人間性が優れていないから評価されないのか?」という可能性も考えるかもしれません。しかし、これはあくまで評価者の視点でそう見えているかどうかの話です。
たとえ本質的に誠実で優れた人であったとしても、評価者の目にそれが映っていなければ、その良さは存在しないも同然とされます。逆に、誠実でなくとも評価者によく映っていれば、その悪さは存在しないも同然です。
人間性の高さそのものではなく、「その人が組織内でどう見られているか」が評価されているという点を、改めて意識しておく必要があります。
ここは、ほぼ言葉の選び方だと思っています。人を見る目に自信がある人でも天才的な詐欺師による言葉巧みな振る舞いには騙されるケースもあります。
実際に心優しい人でも、評価者の評価判定方法では人間性が低いと判定されるような言葉を選んでしまうこともあるでしょう。特にコミュニケーションの場面が限られているのなら尚そうでしょう。
役職を望まない場合の立ち回り

もし役職に就きたくない、責任を避けたいという考えがあるなら、1と2の評価をわずかに下げるという方法もあります。
もちろん、過度にやりすぎれば退職勧告などにもつながりかねませんが、「目立ちすぎず、従順すぎず」というバランスで振る舞うことで、組織内の出世レースから自然に外れることも可能でしょう。
会社側も、評価データをもとに「この人はリーダータイプかどうか」を見ています。その判定において、自ら消極的なサインを出すことで、望まない昇進を避けることができます。
とはいえ、無意味に評価を下げることは、自分の意向が変わったときに後悔しかねないので、自然にやることが一番でしょう。
自分の評価を戦略的に理解する

組織における評価とは、単なる成果主義ではなく、複数のフィルターと関係性によって構築されたものです。 その中で役職が与えられる人には、秩序を守る姿勢(序列意識)、トラブルを避ける安定性、そして周囲に届く仕事の可視性が求められていると思います。
特に、熱意が高い人や仕事に誠実な人ほど、「3で勝負する」と思い込みがちですが、1と2の土台があってこそ評価されることを忘れてはなりません。
そして、評価されないことが即「人間的にダメ」というわけでもありません。評価構造そのものを把握し、自分がどこを押さえて、どこを捨てていくのか。その取捨選択こそが、組織内での生き方を決める鍵になるのです。
役職と評価の構造を理解しておくために

最後にまとめておきます。基本的には、仕事に必要なスキルを高めつつ自然に振る舞いながらも、評価者からの見え方を意識しつつ、組織においての基本ルールを押さえておくとよいでしょう。
- 役職者は無難な人が多い 組織風土とマッチし、波風を立てない人が選ばれやすい傾向。
- 評価されるための見えない前提は3つ 1. 序列を守れるか 2. 面倒ごとを起こさないか 3. 仕事が目立っているか(成果を可視化できているか)
- 実際の評価は成果だけで決まらない 評価者の視点、社内の評判、利害関係など複数のフィルターが存在。
- 人間性の高さ ≠ 評価の高さ 評価者にとって「よく見えるか」が評価に直結する。
- 役職に就きたくない場合は1と2を微調整 従順すぎず、目立ちすぎず。出世から外れる。
- 熱意が強い人こそ、1に要注意 正しさを押しすぎると協調性を疑われる。順序とバランスが重要。
- 評価構造を理解し、戦略的に振る舞うことが鍵 「なぜ評価されないのか」「どうしたら避けられるのか」に答えを持っておくことで、自分のキャリア選択に納得が生まれる。


